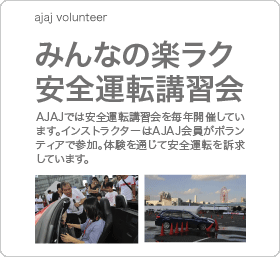沿道にまだ見頃の桜咲く4月10日。1915年創業、今年110周年を迎えた自動車用ランプをはじめ照明技術の分野での革新をリードし続けている株式会社 小糸製作所のご厚意により、AJAJ会員向け勉強会を開催していただいた。

KOITOグループといえば、グローバルサプライヤーとしても有名。13か国30社で構成されており、日本・米州・欧州・中国・アジアを拠点とした世界5極のネットワークを持つ。それぞれの地域ニーズに対応した「お客様第一」を基本に、高い技術を駆使したより良い製品・サービスの提供を行っている。このネットワークを最大限に活用し、最新技術を採用した同品質の製品を同時に供給できるのも強みである。
国内拠点としては、静岡県に4拠点、九州に1拠点、さらに2027年には東北に1拠点を新設予定。全国21拠点に支店・営業所を配置し、国内の全得意先をカバーしている。特に自動車用(二輪車含め)ヘッドランプやリアコンビネーションランプ等の開発・製造そして提供で有名だが、実はその他にも航空・鉄道・船舶用の照明や機器類、信号機等の交通インフラやスタジアム施設照明といった分野においても高い技術を持って対応。我々の身近な暮らしをより快適かつ安全に支えてくれている。
KOITO VISION 2030「進化するランプシステム」をテーマに掲げ、モビリティの安全を一貫して追求するKOITO。勉強会ではドライバーサポート、センシングサポート、コミュニケーションサポートという3つの柱を基本に解説していただいた。その中でも今回はより身近であり、特に興味深かった代表的な技術やシステムについて紹介していこうと思う。
まず、ドライバーサポートとして、ヘッドラップ(前照灯)の進化につて説明が行われた。ご存じのようにヘッドランプはクルマの見た目のデザインを大きく左右する意匠部品であり、安心安全な走行に欠かすことのできない機能部品でもある。ただ明るく遠くを照らしてくれれば良いわけではなく、厳しい保安基準によって性能や試験方法が定められている重要部品のひとつ。ちなみに約2000ページにもおよぶ自動車の構造や装置について規定した技術基準のうち、ランプに関するページ数は20%を占めている。また世界に目を向けると、欧州が主導し国連が制定する「UN規則」、米国が定める「FMVSS」に二分化され、現状それぞれの法規をクリアするための高い技術力、さらに製品の供給が必要となる。もっと先までもっと広く照らす、見たいところがしっかり見える。しかもデザイン性をも求められるヘッドランプは、より効率的な照射範囲の拡大、走行環境に応じた配光制御等によって進化を遂げてきた。

そうした背景の中、早くから高い技術力で時代のニーズに対応しリードしてきたKOITO。ハロゲンからHID、現在主流となっているLEDへと発光効率の向上を目指してきた結果として、効率の良い省スペース性と優れた省電力化を実現。より自由度の高いデザイン性を兼ね備えた商品の提供に成功している。また現行型LEDは2007年世界初の商品化からすでに第5世代まで進化を遂げ、2024年時点での生産比率は国内で87%、グローバルでも82%にまで到達しているという。さらに開発の歴史の中で注目すべきは、もっと広く(側方の照射範囲を拡大、右左折時や曲路走行時の視認性向上)を目的に1983年レビン・トレノに搭載されたコーナリングランプ、1989年の世界初ステアリング連動フォグランプ、2003年これまた世界初となるステアリング連動ヘッドランプを世に送り出した点。加えて車両姿勢が変化しても光軸を自動的に一定に保つオートレベリングシステム、ハイビーム/ロービームの自動切換えを可能にしたSAFETY EYEやAHB(Automatic High Beam)等、こうした革新的かつ画期的なシステムの開発&搭載は、現在の新型車への搭載が急速に進んでいる最新のランプシステムADB(Adaptive Driving Beam)へしっかりと受け継がれている。
ADB(配光可変ヘッドランプ)は、先行車や対向車へ眩しさを与えることなく常にハイビームでの走行を可能にし、ドライバーの前方視界を良好に保つ目的で開発された最新のランプシステム。交通事故死亡者数をデータで見ると年々減少傾向にあるものの、特に車対夜間歩行者との交通事故においてはADBシステムの有効性は非常に高いといえる。また、道交法の改正では「歩行者を早期に視認可能なハイビームを基本ビームと定義」とされた。こうした背景もありKOITOでは、ADBの様々な車種への採用と普及拡大は必須であると考え、歩行者には眩しくない優しさを保ちながら、かつハイビーム作動率の向上という二つの性能の両立を目指し、さらなる微細な配光の実現と低コストの推進に取り組んでいる。

さて、近年のLED化によって発光効率が向上した結果、発熱量が低下。その影響で冬時期のランプへの着雪で困っているというユーザーが増加しているという。この件に関しては当日参加していた斎藤聡会員からも「なにか有効な対策がないものか?」という質問があった。ちなみにKOITOが行った冬場のテスト結果では、ハロゲンランプの表面温度+40度に対してLEDランプは+10度程度の上昇。これでは着雪によりLEDランプ本来の明るさを保てない…早急な対応が求められることに。こうした状況を早期に解決するべく、まずはトラック向けにヒーター内蔵の融雪対応リアランプ(RCL)を2022年11月に製品化。現在その技術を応用する形で融雪対応ヘッドランプの開発が進められている。こうしたユーザーの声や安全性について、より高い技術力を持って貢献している点も目が離せない。
コミュニケーションサポートとしては、最近街中でも見かけるようになったターンシグナルやテールランプに多灯数のLEDを使用したアニメーション動向についての解説があった。特にEV車の普及が進む中国の新興OEMや欧州のプレミアムOEMは、他車との差別化を図るためのアイテムとして積極的にこのアニメーションを採用しているという。KOITOとしてもこうした状況を踏まえ、法規を遵守した上で様々なコンテンツをユーザーの好みで組み合わせが可能なアニメーションを提案。その他にも、安心安全につながる新機能として期待が高まっている、光るインフォメーションを効果的に利用したターン路面描画を先行して開発。その一部新機能ついては、近々日本で初めて市場への投入が予定されている。
勉強会の後半では、ADAS(先進運転支援システム)/AD(自動運転)に貢献するLiDAR(Light Detection And Rangingの略)についての解説。LiDARとは、レーザー光を照射してその反射光を解析、対象物との距離や形状を測定する技術で、前出の先進運転支援システムや自動運転、航空測量など様々な分野で活用されている。KOITOがこのLiDAR事業をはじめた理由は、ランプ技術とLiDAR技術の親和性が高いということがひとつの要因。また測距方式は主に2種類あり、距離、制度、コストなど様々な要因により各社方式が異なっている。詳しい技術的説明は省くが、KOITOはランプで培った光学・放熱・点消灯制御の各技術を活用できるマイクロモーションテクノロジー(メカ式)を採用している。
なぜLiDARは必要? 賛否両論あるが、カメラだけでは正しい判断が難しい交通環境があり、たとえ人の目であっても見間違うシーンが無い、とは言えない。LiDARは、そうした交通環境を3D情報として把握することによって、より高い安心安全につなげるために役立ってくれる。技術面では今年1月に北米のベンチャー企業であるセプトン社を子会社化。それぞれが持つ特徴を生かした共同開発により、シナジー効果を高めアジャイル開発を進めている。ランプ同様、基本構造は賢く共通化しつつ、多様な顧客ニーズ応えるカスタム開発、高い品質と安定供給を実現しているところがKOITOの強みでもある。
またインフラ向けLiDARシステムの活用方法として、子会社であり道路情報システム機器、交通システム機器を手掛けるコイト電工との共同開発によって生まれた、❛光を照らすことで居るのが見える❜を文字った「イルミエル」が紹介された。このシステムは移動体を3Dデータとして検知、認識ソフトを活用することで人や動物、クルマ等に分類し情報を提供できる点が特徴。またコイト電工のコネクションを活用することで、タイムリーに社会実装可能となっている。現時点での採用実績としては、広場や商業施設の人流解析に役立っているという。
ランプ技術の分野で確固たる地位を築き、長い歴史と豊富な経験を活かし、革新を追求し続けてきたKOITO。これからも技術の進歩と環境への配慮を両立したものづくりで、我々ユーザーにより高い安心とより優れた安全を提供してくれるはず。勉強会の開催、ありがとうございました!
キャッチフレーズは…KOITOと、いこう。