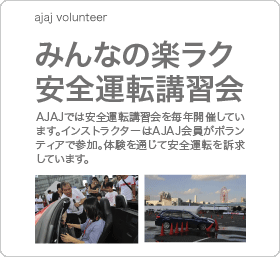BYDの日本における企業の足跡
BYDの日本における足跡
BYDは、いまや中国を代表する自動車メーカーだ。日本には2005年7月に日本法人(ビーワイディージャパン)を設立して上陸し、まずは電気バスやフォークリフトなど商用領域で足場を固めた。 2015年には、中国の自動車メーカーとして初めて電気バスを日本に納入している。
乗用車については、2022年7月に乗用車販売専業のBYD Auto Japan(BAJ)を設立し、実際の販売開始は2023年1月からだ。 2023年1月から2025年6月末までの累計登録台数は5,305台。6月単月は512台で過去最高を2か月連続更新、上半期は前年同期比+167%と伸長している。
そうした影にはイベント露出も大きく貢献している。TOKYO AUTO SALON 2024に出展し、各地のモビリティショーやル・ボラン カーズ・ミート横浜などのイベントでも、乗用車と大型電気バスを並べて見せるなど、エンドユーザー向けの接点づくりを強化している。
また、公共交通でも話題があった。立山黒部アルペンルートの室堂~大観峰区間では、2025年4月15日からBYDの大型電気バス「K8」が“立山トンネル電気バス”として運行を開始。かつてのトロリーバスに代わり、充電式EVバスへの置き換えが完了した格好だ。
BYDバッテリーに就いて
さて、そのBYDを牽引する源といえば、EVの根幹であるモーター…それを動かすエネルギーを蓄える〝バッテリー〟だ。そう聞くと…何やら最新の画期的な新型バッテリーだと想像するだろうけれども、話を聞くと意外にも既存のごく普通の素材をベースに使ったバッテリーだという。ただし、現在普及するEVが採用する三元バッテリー〔レアメタルのコバルト・マンガン・ニッケル〕とは異なり、正極に鉄〔Fe〕を使用した〝リン酸鉄リチウム〟バッテリー〔LFP〕が特徴だ。化学は苦手なので、小学生にも分かる様に要約すると以下の通りだ。
[!NOTE] LFPと三元バッテリーを分かりやすく解説 リン酸鉄リチウムバッテリー(LFP)と三元バッテリー(NCM/NCA)の違いを、お弁当箱に例えて説明しましょう。
?まずバッテリーは「エネルギーのお弁当箱」!
バッテリーは、電気をためて、あとで使うための道具。つまり「エネルギーのお弁当箱」みたいなものだね。
?【LFPバッテリー】=「頑丈なアルミのお弁当箱」
- ?正式名:リン酸鉄リチウム(LiFePO₄)
- ?️メリット:
- すごく丈夫!:ぶつけても、穴が開いても爆発しにくい。
- 長持ち!:お弁当箱が壊れにくいから何回も使える。
- ?️暑さにも強い!:夏の暑い車の中でもへっちゃら。
- ❌デメリット:
- 入るご飯が少ない:ちょっとエネルギーが少なめ。
- 寒さに弱い:冬の寒い朝はちょっと元気が出にくい。
?【三元バッテリー】=「たっぷり入るけど割れやすいガラスのお弁当箱」
- ?正式名:ニッケル・コバルト・マンガン(NCM)、またはニッケル・コバルト・アルミ(NCA)
- ⚡メリット:
- たくさん電気が入る!:お弁当箱が大きくて遠くまで走れる。
- 寒くても元気!:冬でもちゃんと働ける。
- ❌デメリット:
- 壊れやすい:落とすと熱くなって危ないことがある。
- 高い材料を使う:コバルトやニッケルは高くてレア。
? 車での使われ方(2025年現在)
| 用途 | よく使われるバッテリー |
|---|---|
| 安くて安全で近くに使う車 | LFP(BYD、テスラの標準モデルなど) |
| 長く走る高級車や寒い国の車 | 三元系(テスラ上位モデル、日産アリアなど) |
?まとめ(超ざっくり)
| 項目 | LFPバッテリー | 三元バッテリー |
|---|---|---|
| 丈夫さ | ? 強い | ? 弱いときも |
| 電気の量 | ? 少なめ | ? 多い |
| 値段 | ? 安い | ? 高め |
| 寿命 | ? 長い | ? 普通 |
| 寒さ | ❄️ 苦手 | ❄️ 得意 |
だからね、 – 「安全で長く使いたいならLFP」 – 「たくさん電気が必要で速く走りたいなら三元系」 —
BYDは“SDV”の実践者──クルマの価値をソフトで変える時代へ
「SDV(Software-Defined Vehicle)」とは、ざっくり言えば“ソフトウェアで定義されるクルマ”のこと。最近の車はどれもコンピュータ制御じゃないの?──という声が聞こえてきそうだが、それとはちょっと意味が違う。
これまでは、車の中にソフトウェアが載っているだけで、基本的にはハードウェアが主役。ところがSDVは逆で、クルマの性能や機能を“あとからソフトで変えられる”という思想がベースになっている。
たとえばBYDが採用しているOTA(Over The Air)アップデートは、スマホのようにソフトウェアが勝手に進化していく仕組み。従来のようにディーラーへ足を運んで更新作業する必要がなく、ある日ふと気づくとクルマの挙動が改善されていたりする。ユーザーにとっては、これが意外とありがたい。
気になるサイバー攻撃対策は?
クルマがインターネットにつながるなら、当然サイバー攻撃のリスクも気になるところ。BYDはその点も抜かりがない。
国際連合欧州経済委員会(UNECE)が定めたR155(サイバーセキュリティ)とR156(ソフトウェア更新管理)の認証をすでに取得済み。OTAアップデートが安全に行える体制が整っている。
EV最大の不安──バッテリーの寿命
EVが普及フェーズに入る中で、どうしても避けられないのが「バッテリーは何年もつの?」という疑問だ。
これまでの内燃機関車なら、エンジン音や整備履歴で“だいたいの寿命”が見えていたが、EVはそうはいかない。バッテリーの健全性(SoH)は見た目では判断できず、「まだ大丈夫」と思っていても性能がガクッと落ちてることもある。ここにスコトーマ(心理的盲点)が潜んでいる。
BYDの答え──バッテリー保証制度の充実
BYDはこの懸念に対して、しっかり手を打ってきた。
まず、新車ユーザー向けには2025年4月から10年/30万kmのSoH延長保証プラン(有償)を用意。これは「70%以上の初期容量を保つ」ことを保証するもので、標準保証(8年/15万km)よりぐっと安心感が増している。
さらに、2025年6月からは認定中古車にも同じ保証を無償で適用するプログラムをスタート。新車と同様に、SoHが10年間保証されるのは中古EV市場にとっては画期的な試みだ。前オーナーの使い方に関係なく、しっかりした保証がつくことで中古車購入への不安を大きく減らしてくれる。
加えて、定期点検や消耗部品交換がパッケージ化された「BYD eパスポートライト」も利用可能。新車も中古車も、長く安心して乗ってもらうためのサポート体制がじわじわと整ってきた。
まとめ:クルマは“買って終わり”じゃない
SDVの時代において、クルマは“買ったあとから進化する道具”になりつつある。BYDはその変化をいち早く捉え、OTA、セキュリティ、そしてバッテリー保証という三本柱でユーザーの不安を先回りして解決しようとしている。
特に、中古EVでも10年保証がつくという安心感は、今後の市場において強い武器になるはずだ。
「使ってからが勝負」──そんな時代のクルマ選びに、BYDは十分に応える存在になりつつある。
| ■参加者(敬称略、五十音順) 47名 |
|---|
| 会田 肇 /有元正存/ 石井昌道/ 石川真禧照/ 一条孝/内田俊一/太田哲也/大谷達也/岡崎五朗/大音安弘/岡本幸一郎/加瀬幸長/片岡英明/桂 伸一/工藤貴宏/菰田潔/斎藤 聡/斎藤慎輔/佐藤久実/佐藤耕一/塩見 智/島崎七生人/鈴木 直也/瀬在仁志/高橋アキラ/高山正寛/滝口博雄/竹花寿実/近田茂/中村孝仁/ 西川昇吾/西村直人/萩原秀輝/萩原文博/橋澤宏/ピーター・ライオン/藤島知子/堀越保/松田秀士/ 桃田健史/森川オサム/森口 将之/諸星陽一/山崎明/山城利公/吉田由美/ピーターライオン |